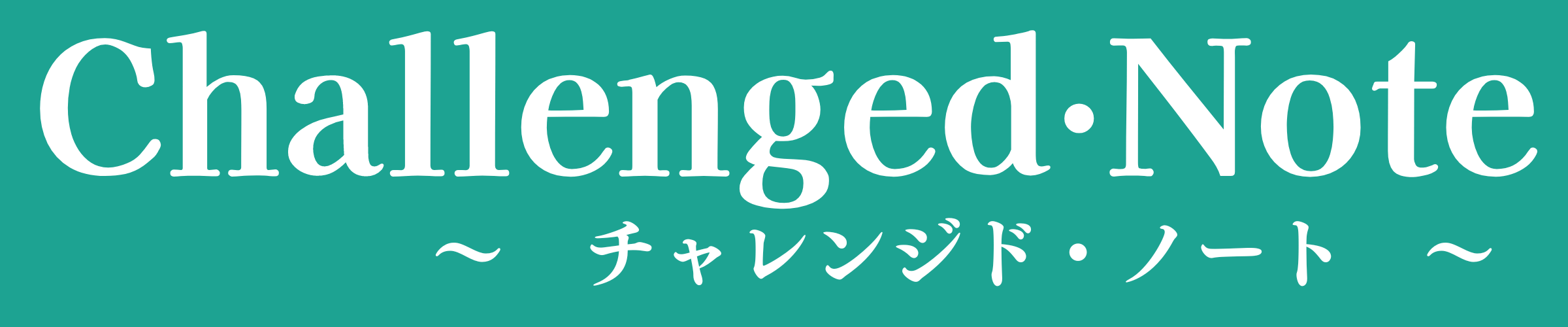記事内にプロモーションを含む場合があります。
ASDの方やADHDの方の場合は、適職診断などもあるため、比較的簡単にわかります。
ですが、ASDとADHDを併発している場合はどうでしょうか?
ASDとADHDの両方を併発している発達障害の持ち主の場合、特性が人による部分も多いので適職見極めるのが困難です。
今回は、ASDとADHDの併発している方に向いている職種を紹介していきます。
※あくまで今回紹介するのは一例です。自身の障害特性に適した職種は、専門機関などで検査を行い、見つけるのが一番だと思います。
ASDとADHDが併発する発達障害
発達障害は一般的に、ASD、ADHD、LDに分かれており、その障害特性は大きく異なります。
しかし下記の図にあるように、発達障害は併発する可能性もあるため、「ASDの方でもADHDの特性を持つ」というケースがよく見られます。
ではASDとADHDを併発している場合、どのような仕事が適職といえるのでしょうか?

筆者もASDとADHDを併発しています。当事者目線での回答をしていきますね!
まずは、ASD・ADHDそれぞれの適職を見ていきましょう。
ASDに向いている仕事は?(適職)
ASDに向いている仕事を紹介する前に、まずはどのような障害特性があるかを見ていきましょう。
ASDは一般的には、「場の雰囲気を読むのが苦手」「特定のジャンルへの興味」を上げられるケースが多いです。ほかにも人によっては「感覚過敏」が見られる場合もあります。
これらの障害特性を踏まえた適職として、下記の職種が挙げられます。
・プログラマー
・清掃/軽作業
・研究職
・翻訳家
・アーティスト
・写真家/イラストレーター
・デザイナー
・ライター
・財務・経理・法務
逆に向いていない職業は下記の職種です。
・接客業
・営業職
・調理師
・SE
・企画職
ASDには特定の分野への興味を生かした仕事や、ルール・時間が決まっている職種が向いているとされています。
そのため事務の中でも法務・経理職や理系なら研究職などが適している職業です。
他にも作業系のライン作業や清掃が挙げられます。
一方で、ASDの場合はコミュニケーションや臨機応変な対応を求められる職種は向いていないケースが多いです。
※企業によってはマニュアル化されている場合もあります。
また、SEの中でも顧客との会話が多い場合はあまり適していないといえるでしょう。
※事務の中でも会議の多い企画職も同様です。
ADHDに向いている仕事は?(適職)
ADHDの障害特性は下記のとおりです。
ADHDの場合は、「多動性」「注意欠如」の障害特性が挙げられます。具体的には「うっかりミス」「じっとしていることが苦手」などです。
そして、ASDと共通しているのが特定の分野へのこだわりです。
※ASDのほうがこだわりへの執着は高いですが、ASDHの場合もみられることが多いです。
得意なこととしては、自由な発想や人によってはコミュニケーション能力が高いことがゲラれます。
ADHDに向いている職業は下記の職種が挙げられます。
・料理人
・プログラマー/エンジニア
・デザイナー(アーティスト系)
・研究者
・塾講師
・人事
・営業
ASDはADHDと異なり。コミュニケーションに重点を置いた職種が向いているケースが多いです。特に自分の興味のある分野へのクリエイティブさが求められる仕事も向いているでしょう。
一方で向いていない職種としては下記の職種が挙げられます。
・経理/法務
・公務員
・関係
・ライン作業/清掃
ルールや規則が多く、ミスが許されない仕事がADHDの特性上苦手な場合が多いです。
また、仕事場の雰囲気としても在宅勤務などが少なく、お堅い雰囲気の公務員などは向いていないでしょう。
ASD+ADHDを併発している場合の適職は?
ASDとADHDそれぞれの適職を見て、共通する仕事は下記の通りです。
・デザイナー(アーティスト)系
・プログラマー
・ライター
両者ともにこだわりが強いために、専門職もしくは芸術的感性が求められる職種が、ASDとADHD両方の適職として挙げられます。また、これらの職種は在宅勤務が可能であり、仕事場の雰囲気などの縛りを受けません。
こういった点もASDとADHD共通して向いている職業として挙げられた理由かと思います。
難易度が高い職種ばかりで就職が難しい、という方も多いでしょう。
筆者の見解としては給料アップを目指したいならプログラミングを学んでプログラマーに、給料を気にしないならクラウドワークスなどのクラウドソーシングでライターを経験するのが良いかと思います。

未経験から仕事を受注できるライターの仕事は多いので、クラウドソーシングサービスでまずは探してみるのがおすすめ!
※プログラミング・デザインなどは就労移行支援で習得することも可能です。
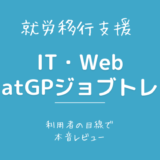 【利用者の作品も紹介します】atGPジョブトレIT・Webの口コミ・評判徹底調査 | 就労移行支援
【利用者の作品も紹介します】atGPジョブトレIT・Webの口コミ・評判徹底調査 | 就労移行支援 ASD+ADHD向けの転職エージェント
ASDとADHDの併発の方が就職される場合、配慮をもらうなら「障害者雇用」である必要があります。
障害者雇用は「障害者手帳を保持している」方が、配慮をいただきながら働く雇用形態です。
※障害者手帳の所有が条件になります。
もちろん一般枠(障害をオープンにしないことも可能)で働くこともできるので、自分に合った働き方を見つけてみましょう。

転職エージェントは仕事選びの相談にも乗ってくれるので、まずは悩みを相談してみよう!
※障害者雇用・障害者枠での就労は、「障害者手帳を所有している方のみ」が対象となっています。手帳を所有していない方は、一般枠の就労サービス・エージェントを利用しましょう。
・首都圏・関西マイナビパートナーズ紹介 ![]() (おすすめ)
(おすすめ)
・全国dodaチャレンジ![]()
・首都圏+大阪障害者雇用バンク
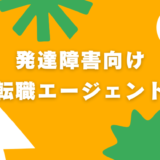 ≫発達障害に向いてるのはこれ!おすすめの障害者雇用転職エージェント&求人サイト
≫発達障害に向いてるのはこれ!おすすめの障害者雇用転職エージェント&求人サイト もし仕事が続かないなら就労移行支援へ
「ASDとADHDが併発しているので、仕事が続かない・・・」という場合には、すぐに仕事に就くのではなく、就労移行支援に通所しながら適職を見つけていくのがおすすめです。
就労移行支援では、各障害の特性や配慮事項・適職について勉強しながら就職に向けた訓練を行うことが出来ます。
せっかく就職したのに定着しなかった・・・となっては勿体ないので、定着率を上げるために訓練を行う方がいいでしょう。

就労移行支援では見学を行っている事業所が多いので、まずは雰囲気だけでもどのようなところか見てみましょう!
ASDとADHD併発の適職まとめ
今回はASDとADHDを併発している方の適職に関して紹介しました。
発達障害の障害特性は人によって異なるので、必ずしも今回紹介した事例には当てはまらないかもしれません。
より自分に合った仕事について知りたい場合には、専門機関で検査を受けたり、就労移行支援に通所して見つける必要があります。
時間がかかるとは思いますが、上手くサービスを活用して、自分の向いている仕事・職種を見つけていきましょう!
当サイトでは、障害者向けのコンテンツを掲載しています。就労移行支援や転職エージェントについてはTOPページよりご覧ください。
よく読まれている記事
あわせて就労移行支援おすすめランキング
あわせて発達障害専門の就労移行支援
あわせて障害者専門の転職エージェント
就労移行支援の口コミ・評判まとめ
障害特化型就労移行支援
総合型就労移行支援
IT特化型就労移行支援
・atGPジョブトレIT・Web おすすめ
就労移行支援の比較
| 就労実績 | 定着率 | 事業所数 | 対応エリア | 対象障害 | |
|---|---|---|---|---|---|
| LITALICOワークス | 累計就職者数10,000名以上 | 90% | 110か所以上 | 北海道 / 仙台 / 栃木 / 埼玉 / 千葉 / 神奈川 / 東京 / 静岡 / 愛知 / 京都 / 大阪 / 兵庫 / 岡山 / 広島 / 福岡 / 宮崎 / 沖縄 | 精神・発達・知的・身体・難病 |
| Kaien | 累計就職者数1,400名以上 | 94.9% | 14か所 | 東京 / 神奈川県 / 埼玉 / 大阪 | 発達 |
| ミラトレ | 就職率85% | 90% | 14か所 | 東京 / 神奈川県 / 千葉 / 埼玉 / 大阪 / 兵庫 / 愛知 | 精神・発達・知的・身体・指定難病 |
| atGPジョブトレ | 1事業所当たり24名(年間) | 91.4% | 7か所 | 秋葉原 / 大手町 /お茶の水/ 横浜 / 梅田 | うつ症状・発達・統合失調症・聴覚障害・難病 |
| ココルポート | 累計就職者数2,400名以上 | 88.2% | 60か所以上 | 東京 / 神奈川県 / 千葉 / 埼玉 / 福岡 | 精神・発達・知的・身体・指定難病 |
| welbe ウェルビー | 累計就職者数5,032名以上 | 89% | 97か所以上 | 東京 / 神奈川 / 千葉 / 埼玉 / 高崎 / 宇都宮 / 静岡 / 愛知 / 大阪 / 京都 / 兵庫 / 岡山 / 広島 / 松山 / 福岡 / 熊本 / 鹿児島 / 札幌 / 仙台 / 新潟 | 精神・発達・知的・身体・指定難病 |
| d-career ディーキャリア | 非公開 | 93.4% | 70か所以上 | 東京 / 神奈川県 / 千葉 / 埼玉 / 大阪 / 愛知 / 福岡 | 発達 |
障害者専門転職エージェント
・首都圏・関西マイナビパートナーズ紹介 ![]() (おすすめ)
(おすすめ)
・全国dodaチャレンジ![]()
・全国LITALICO仕事ナビ ![]()
・首都圏+大阪障がい者雇用バンク
オンラインカウンセリング
当サイトの参考リンク
就労移行支援・就労定着支援に係る報酬・基準について:厚生労働省
障害者の雇用支援:高齢・障害・求職者雇用支援機構
障害者雇用の現状:文部科学省
<免責事項>
当ブログからのリンクやバナーなどで移動したサイトで提供される情報、サービス等について一切の責任を負いません。
また当ブログのコンテンツ・情報について、できる限り正確な情報を提供するように努めておりますが、正確性や安全性を保証するものではありません。情報が古くなっていることもございます。当サイトに掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。